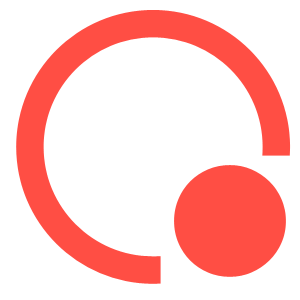西部戦線異状なし エドワード・ベルガー
Netflixで鑑賞「西部戦線異状なし」
残酷なほど美しい映画だった。残酷さと美しさ。
1929年に出版された原作を、翌年1930年に早くも映画化された作品とこの映画で比較すると、原作が同じなので当然に大筋は変わらないが、映画としての狙いは全く異なる。別の映画である。1930年作品のマイルストン作品は、極めて情緒的で詩的な表現が多く、特にラスト、蝶に手をのばして主人公が死んでゆくシーンは極めて感動的だが、本作は究極のリアリズムを追求している。そのあまりにも残酷なシーンの臨場感が、映画全体の美しさと対比的だ。
この映画の表現は、対位法で貫かれている。
残酷なシーンときれいな風景。戦場の残飯と将軍たちが食べる温かみのある料理。生きるか死ぬかという対比の中で、戦場の現実が映し出される。1930年作品と重なるシーンは多くないが、冒頭の戦意高揚を煽る教室のシーンと、主人公パウル(1930年ではポール)がフランス兵を刺し殺して、ポケットから家族の写真と取り出すシーンはほぼ同じ。これらを除けば、ほとんど別の物語のようだ。

特に強調されるのが、戦場で腹をすかした兵士たちの現状。平原を移動する途中、民家からニワトリや卵を盗んで逃げるというシーンを含めて、命がけで食べるために奔走するシーンが印象的だ。負傷した仲間にスープを与えたら、フォークで首を刺し自殺するというシーンは、「食べる=生きる」ことの対比ともとれる。こうした泥臭く血なまぐさいシーンの反対で、将軍たちは自らの名誉のためだけに兵士を戦場に送り込み、その傍らで何不自由のない生活でうまい料理を口にしている。パンが暖かくないことにクレームをつけるシーンなど、腹立たしく思えるシーンが多い。
これは、明らかに為政者の愚かさを示すものだ。第一次世界大戦前の帝国ドイツから第二次世界大戦が終結するまでのドイツを象徴的に描くこの映画は、時々現れるドイツの将軍を痛烈に批判するものだ。これは1930年作品では示されなかった部分である。停戦合意後も愚かな進軍をする将軍と、その号令により命を落とす兵士。夜営で主人公のパウルが仲間と会話する中で「神は見ているだけだ。」とは本音だろう。この場合の神は将軍である。戦場で兵士が次々と命を落としている間、指導者は暖かいスープを口にしている、というドラマだ。

冒頭の描き方も見事。美しい草原を描写し、直後に兵士たちの死体を流れるようにカメラがとらえ、遺体が荷物のように運ばれる過程で軍服が脱がされ、その軍服はお針子さんたちがミシンをかけて再利用する。新兵に軍服が供与されると、その軍服を以前使っていた兵士の名前のタグがついている。パウルは「これは違う人の軍服です。」と主張すると係官がそのタグを外して床に捨てる。これらのシーンで映画のほとんどは語りつくされている。要するに兵士は使い捨てなので。次から次へと戦場へ送り込まれる兵士は、学校で与えられた高揚感ではじめは活き活きとしているが、いざ戦場に赴けば、その現実に翻弄されてゆく。
★
こんなブログもやってます(=^・^=)
KINENOTE
Filmarks
goo
FC2
Muragon
seesaa
Livedoor
楽天ブログ
ameba
wordpress
Hatena
にほんブログ村
人気ブログランキング
Twitter
Facebook
ブロトピ:映画以外の記事で!ブログの更新をブロトピしましょう!!
政治経済 新聞記事 グルメ日記 スポーツとダイエット 愚痴 旅行散歩 映画読書